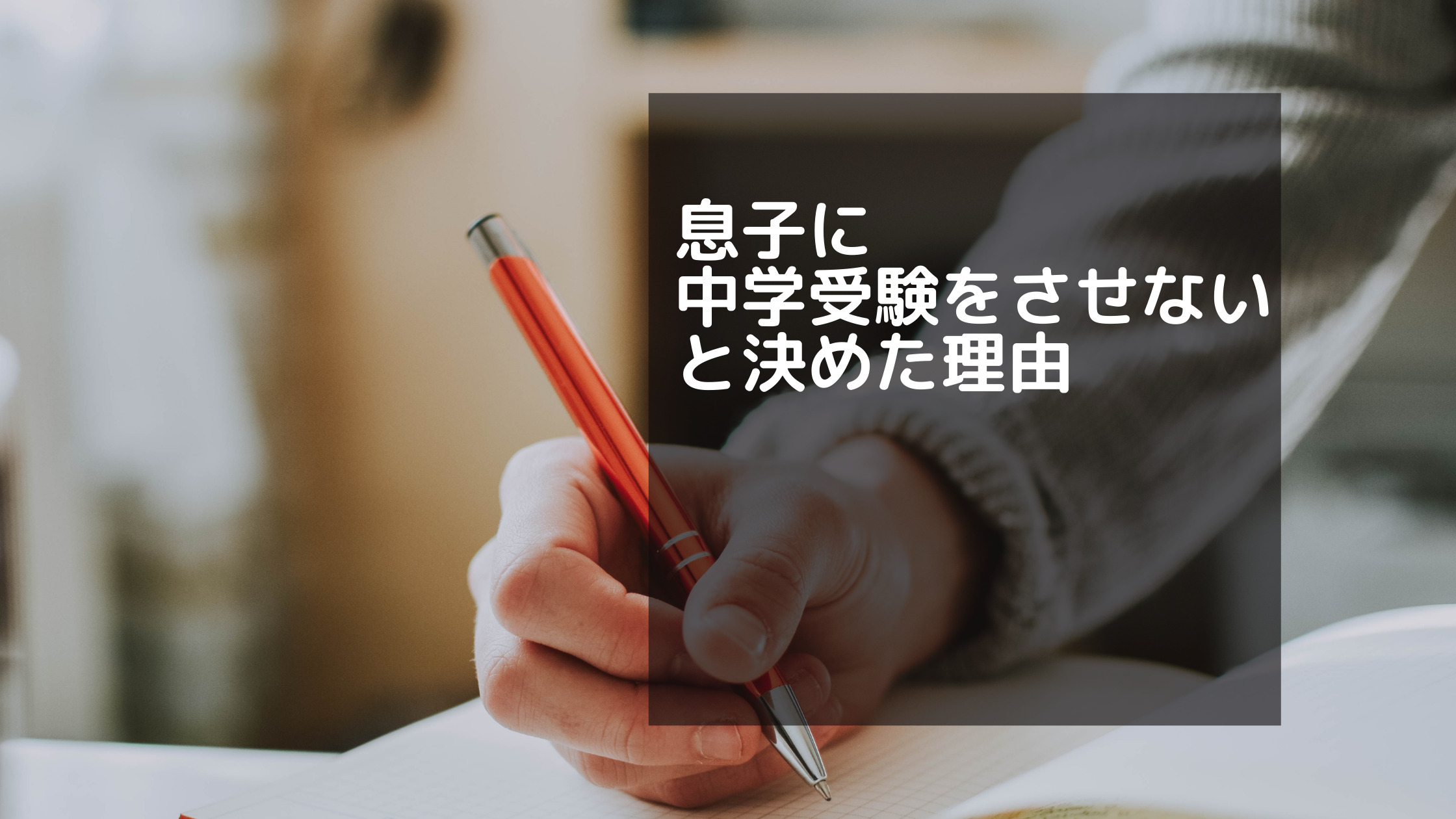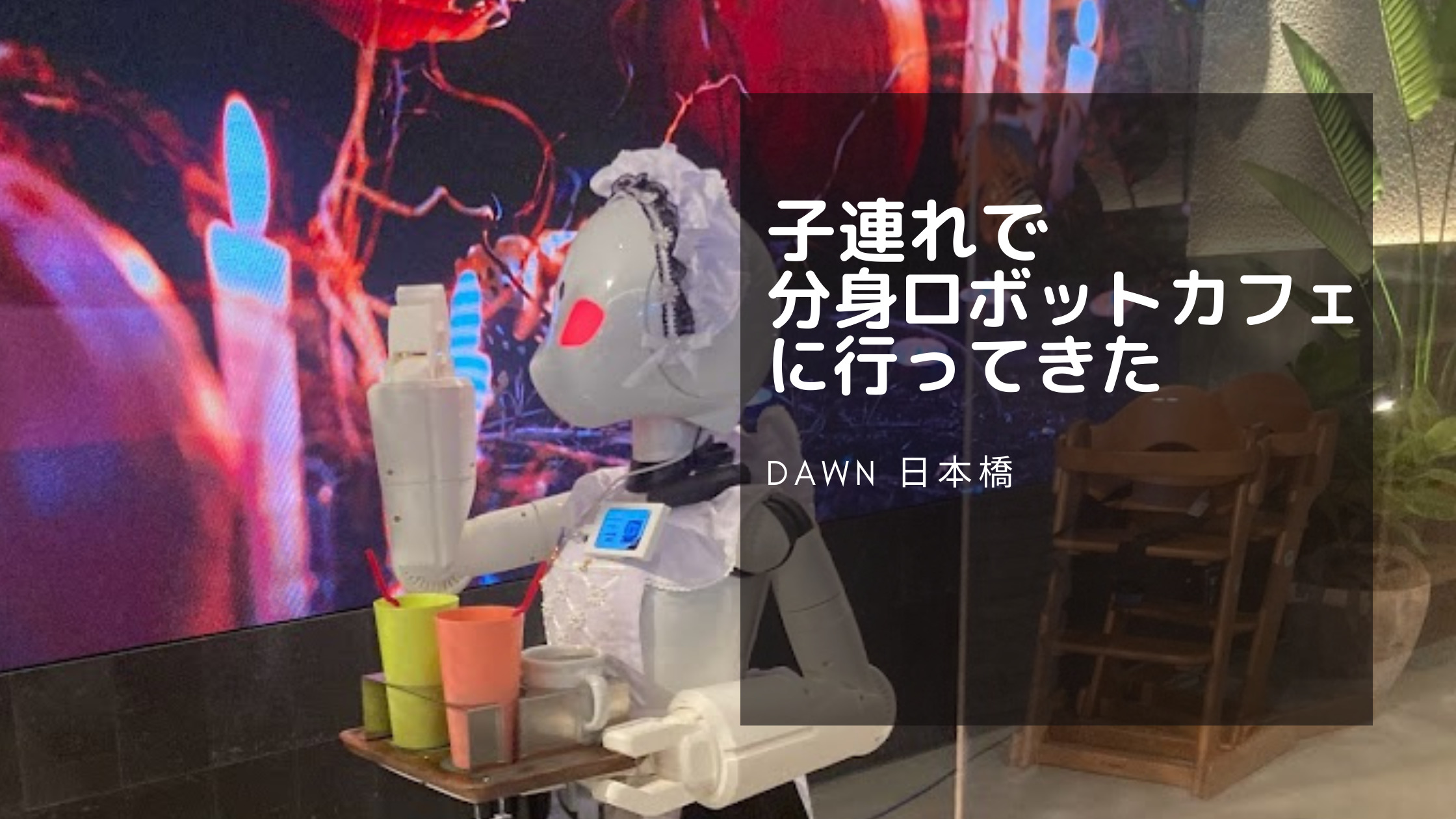こんにちは、ワーママpicaco(@wmpicaco_)です。
公立小学校に通う上の子(息子)がもうすぐ4年生になります。中学受験をするなら、小3の2月から受験塾に通うのが首都圏のスタンダード。通塾の時期は年々早まっているとも言われています。
ということで、我が家にも息子に中学受験をさせるかどうかを決める(決めなければならない!)時期がやってきました。さんざん悩んできたけど、結果、中学受験はさせない方向で行きます。今回はそのように決めた理由をまとめておこう思います。
決め手は最近読んだ中学受験テーマの小説「翼の翼」…というのは冗談ですが、この小説はリアルを少なからず反映してるんじゃないかな~と思って面白かったです。
目次
これまでの悩み具合
我が家は首都圏に住んでいて、まわりも中学受験をする人がとても多いです。元々ここは私の地元で、当時(30年前…)もちらほら中学受験をする子はいました。それでもクラスに1~2割ぐらいだったかと思います。私は公立小→公立中→公立高 の進路を進みました。
最近は、友達の子も親戚の子も、中学受験をしてその話題を耳にすることも多く、私も我が子の就学前からずっと気にしてきました。子どもの通う公立小学校でも受験組が半分以上はいる模様。
子どもは登校班で学校に通っていますが、その登校班に昨年、6年生が5人いて、そのうち4人が受験組でした。(親しいわけではなくても、1月下旬から2月頭まで休んでいたのでわかりますね~。) やはり、実感値としても受験率が高いです。
中学受験、親も子も大変そう。でも、中学受験をさせないことで子どもの可能性を狭めてしまうのでは?やっぱり、環境は大事。少しでも学力の高い、学習意欲の高い友達に囲まれて学んだほうが子どもにとって良いのでは?公立中に行って朱に交われば赤くなる、ってことで非行に走るかも… ウンタラカンタラ…とか、めっちゃ悩みました。
こうも受験組が多いと、「うちは公立で行く!」と意志をよっぽど強く持たないと、不安からなんとなく塾に通わせてそのまま流れに乗って受験ルートに流される..という気すらしてきます。
本もたくさん読んできました。
中学受験する?しない?まだ未就学児だけど勉強のために「中学受験は親が9割」を読んだ
「早慶MARCHに入れる中学・高校 親が知らない受験の新常識」を読んで最近の受験事情を探る
おおたとしまささんの中学受験本「受験と進学の新常識」「中学受験という選択」を読んだら中学受験に魅力を感じてきた
「危ない中学受験」という本を読んで我が子の中学受験について考えた
AERA(2020年1月27日号)を読んで公立中高一貫校という選択について考える
いろいろ読んで考えた。でもやっぱり一番見なきゃいけないのは目の前にいる我が子、ですよね。この子にとっては何が合っているのか?良いところを伸ばす環境、幸せに生きていくためには?ってことにつきます。
息子を見ていると、正直、ぜんぜん中学受験、という感じがしなくて、この子に中学受験をさせるのは無理やり感がすごい..
以下にいろいろ理由を書きますが、まとめるとそういうことかなと思います。
理由1 机に向かう勉強が好きではない。
息子には小1から通信教育のZ会をやらせて、毎日の学習習慣をつけてきました。現状なんとか習慣はついていますが…毎日嫌々やっています。「これをやらないとyoutubeが見れない、ゲームができない」から、親に言われてやっている。それだけという感じ。ま~~、そんなものなのかな。
私も勉強は全然好きではなかったので気持ちはわかる。
そして、今のところの息子の学力は、相対的に見て平均より下のほうだと思います。その点を見ていてどうしても親の私に焦りが生まれてしまいます。結果、毎日の勉強をやらせるたびにガミガミ言ってしまい、息子は反発する、の悪循環…
自分自身「勉強しろ」と言われて育ってきて、勉強嫌いになったので、そう言わずに育てたかったのに、息子の様子を見ていると言わずにいられない、、という葛藤の毎日です。
息子が、中学受験の勉強量に前向きに取り組める未来はどうしても想像できないし、思う通りに取り組まなかった時に自分が冷静でいられる気がしません。
理由2 子どもの進路のレールを親が敷くことに対する違和感
こんな様子なこともあって、息子に「中学受験をさせる」というのは自然の摂理に逆らう感じが強い。「公立中に進学する」という方針だって言ってみれば親が敷いたレールではあるけれど、中学までは義務教育なわけで、そっちのほうが息子にとってはまっすぐなレールに思えます。
なにせ「中学」とか「受験」がなんなのかよくわかっていない子どもに対して、それに向かって誘導するところから始まるのが中学受験だと思っていますが、お金も時間もたっぷりかかるそんな誘導をするのは今じゃない感がすごくあります。
自分の進路は自分で決めてほしい。「この学校に行きたい!」「この勉強がしたい!」「こうれがしたい!」と自分で思って初めて、自分で選んだレールになるのだけれど、息子がそのようなことを考えられる時期がこの3年以内に来るとは思えないのです。
ならば、小学生の間は受験勉強ではないことに時間を使うほうがいいかな、と考えています。
理由3 (親の私が)偏差値信仰を捨てられない
結局、恥ずかしながら「中学受験をするなら偏差値の高い学校に合格しないと」と思っている自分がいることも大きい。
自分がいわゆる偏差値の高い高校、大学に進学して、家族もみんなそういう感じで、そのおかげで今の自分があると思っているために、「偏差値の高い学校に行くことがいいこと」という考えを捨てることができない… 本当はそんなことないのに。
こんな私と、現在の息子の様子を見ていると、中学受験に親子で円満に臨める希望が持てないです。
だから、子どもには親の考えなんか突き抜けて、自分で自分の道を選んでいって欲しいと思っています。(=理由2)
理由4 「公立中学」の多様性は経験する価値がある
これもまた、単に自分の経験の肯定からの考えにすぎないのだけど、私は公立中学でいろんな学力、いろんな家庭環境、いろんな考え方の友達の中で過ごした経験が、その後の人生にとって有益だったと感じています。
受験をして入学する中学だって、別の意味で多様性はあると思います。でも、社会の縮図にはなってない。受験という尺度の中で選ばれた子どもたち、だけしかいない。そうではない環境に身を置くことには価値があると思っています。
それから、私は自分の自己肯定感は、公立中にいったから育まれた面もあるかもしれないと思っています。中学の友達からしたら「すごい勉強ができる人」だと思われていた。大学ではそんなことはなかったけれど。たまたま私にとってはそれが勉強の面だったというだけで、自分と友達とを比べて比べて比べる時期、「選ばれてない」環境で自分と他者を比べることも悪くないのではなかろうか。
はぁ。一生懸命考えて決めたけどこれでいいのかな、っていつだって迷っている。
子育ての悩みは尽きませんね~。
下の子はまた全然様子が違うので、もしかしたら下の子は中学受験もあり得ると思っています。
冒頭で紹介した中学受験小説はこちら。
wmpicaco
最新記事 by wmpicaco (全て見る)
- 皮の厚い柑橘類を簡単にむく!夏みかん・いよかん・はっさくに便利な「ムッキーちゃん」 - 2023-05-19
- 大豆ミートの魅力とは?ヘルシーで経済的な代替肉の使い方 - 2023-05-18
- 便利で清潔!サラダスピナー代わりに蓋つきボウルとざるを活用 - 2023-05-17