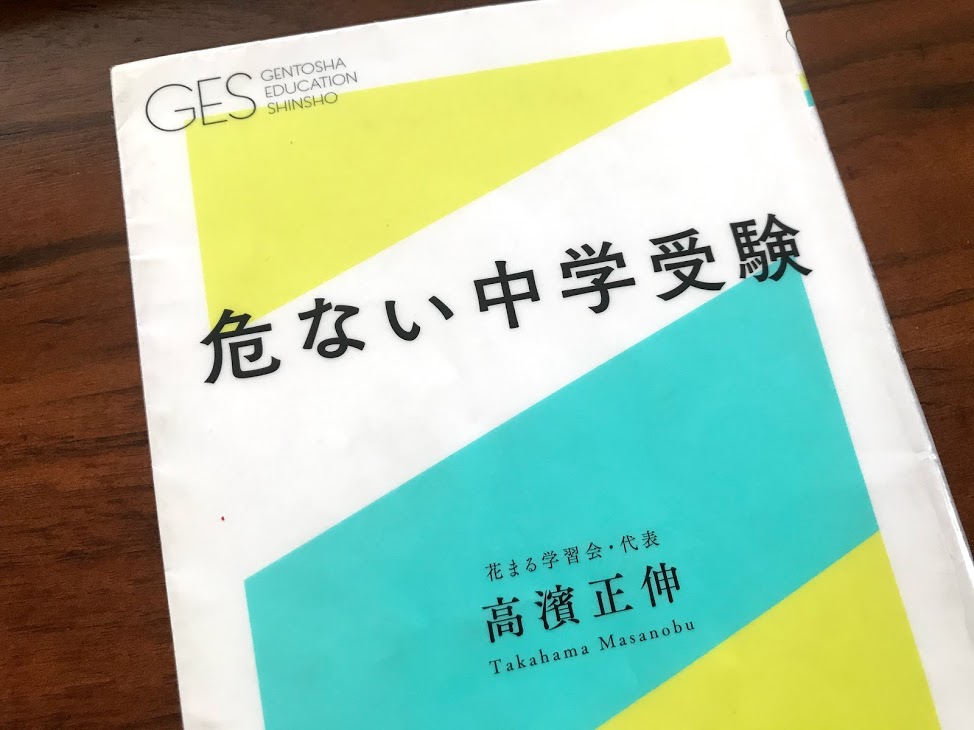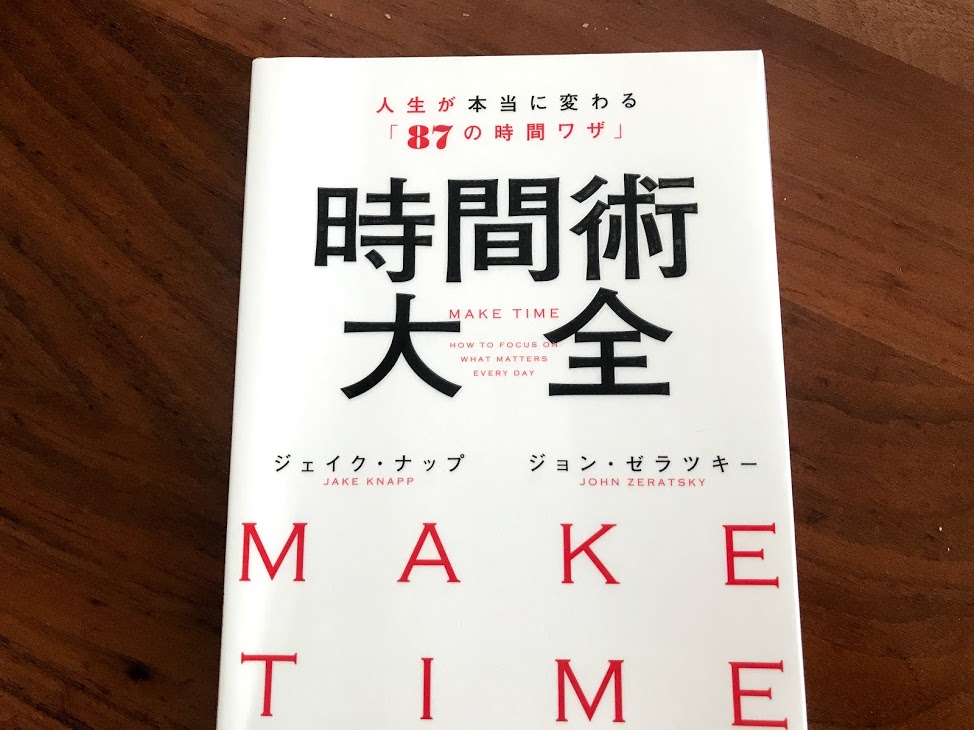こんにちは、ワーママpicaco(@wmpicaco_)です。
そんな中、花丸研究会代表の高濱正信さんの著書「危ない中学受験」という本を読みました。
1 中学受験で身につくもの
本では以下のように述べられている。
ノートの付け方などの学習習慣、また本質的な力としては思考力が挙げられ、これらは一生役立つ力となる。
中学受験で向き合う算数の図形問題や文章問題には、思考力が求められる問題がたくさんあり、思考力問題に立ち向かう中で、子供たちは論理力、国語でも求められる要約力も身につけていく。』
中学受験に挑む小学生の学習量や努力量をを見ていると、半端じゃない量をこなしている様子。中学受験の経験がなく、大学受験でも理系科目しか使わなかった私からすると、若干10歳前後にして到底大人でも及ばないような量の知識と努力をしているんだなと驚いてしまう。
既に中学受験を終えた姪の話や、数年後に受験を控えた友達の子の話を聞いていても、平日夜の塾通いに加えて、お正月や夏休みの特訓、その過程で身につく歴史や地理、理科の学習項目を聞くだけでも圧倒されるほど…
当然、その努力で得るものは本にも書かれているとおり、それ以後の人生でも活かせるような貴重なものとなることは理解できる。
本で書かれていた「思考力」や「学習の型」の話とずれるが、例えば姪は歴史が好きで、受験勉強の傍らで歴史的ないわれのある土地を訪ねたり、大河ドラマや歴史小説を楽しんだりしていた。知識のある分、物事の見え方が鮮明になるし、それが早い分、人生が豊かになるということは多分にあるのではないかと思う。
2 中学受験で失うもの
一方、失うものは何かについては以下の通り。
『中学受験で失うものがあるとしたら、時間とお金、そんな言葉を思う浮かべるとしたら少しそれは違う。そもそも受験勉強に費やした時間とお金は前述のような貴重な体験を積んだことで十分にトレードオフになっているはず。
もし受験勉強の間に何らかのマイナスの影響が子供に生じるとしたら、それは学ぶ楽しさを失ってしまうこと、これは親が十分に注意をしなければならない。』私自身、あまり学ぶ楽しさを感じることができずに学生時代を送ってしまったこともあり、子どもにはなるべく、勉強を押し付けるようなことはしたくないと思っている。受験塾の先生は教え方が上手で「楽しい」と感じている子が多いように見えるけれど、そう感じられるかどうかは子どもによると思う。
『たとえ勉強があまり好きでない子でも、少しずつ分かった喜びや、できちゃった快感を体験していれば、達成感や自己肯定感を持ちながら勉強に向き合うようになるもの。
ただ出来た出来ないという観点だけで、子供を評価していると問題が解けなかったり、成績が上がらない時に子供は自分がダメな子だと敗北感を背負うようになる。』
このようにも書かれているとおり、受験勉強を通して子どもが達成感を感じるようになれば良いけれども、接し方によっては逆効果になることは十分に覚えておきたいと思った。
また、公立中学を避けるために中学受験をさせて、どこかで親がて安心したいという考えも多いような気がする。そのことについても触れられていた。
『同質の家庭環境や価値観のもとで育った子は、生活、行動習慣や性格もどことなく似ている。そうした集団の中で我が子が学校生活を送ることは親としては安心。
異質なものとの遭遇が、世界観を広げ、自分を一回り大きくしてくれる。
これまでの自分の価値観や考え方をゆさぶり、ときには180度覆すような異質なものとの出会い。それが人間としての成長の糧となる。』
これについては、私もある時までは安易にそのように考えていたのだけれど、私立でも別の意味で異質の友達との遭遇があったり(例えば自分には手の届かないようなお金持ちや、圧倒的な才能の持ち主など)、世界観を広げる体験はできるのではないかとも考える。住む場所一つとっても、公立のほうが範囲が狭いよね?というコメントをどこかで見かけて、それもそうだな、なんて思ったりもしている。
3 我が子が中学受験に向いているかどうかの判断基準
これは非常に参考になると思った。
中学受験では、大人性ともいうべき早熟な感性が問われる。早熟タイプのほうが圧倒的に有利。大人性は一朝一夕に身につくものではない。教えられて覚える技能とは異なり、人間の成長と共に育まれる精神性が問われる。
負けず嫌いは、勉強でもどんどん伸びる可能性や秘めている。
例えばうちの子はかなりの負けず嫌いで、負けるとやる気を失ってしまい扱いづらいと思っている。これをうまい方向に活かせればいいなと前々から思っていた。勉強でも伸びると言われると期待してしまうが、働きかけ方次第なのだろうなと思う。
精神的発達は5年生の後半や6年生で驚くほど変化を見せることがあり、6年の夏場が最終判断の時期、とのこと。
4 子どもへの働きかけ方
途中で受験をやめる可能性があったとしても、そのことを子どもにはあらかじめ言う必要はない。最初からやめる可能性があることを知っていると必死さが失われるからだそう。そして決断の際は子どもの自尊心を傷つけないよう、反応を見ながら上手に伝える必要がある。
この本では公立中学を選択することの肯定的な材料として、「有名企業の社長の出身校は私立より公立がかなり多かった(週刊現代の2014年調査)」という内容にも触れていた。この調査に関しては、今既に社長になっている人の学歴と、現在小学生の子供達の学歴ではまた事情が違うのでは?という疑問がわいた。
こういった様々な観点で環境や自分の教育方針を俯瞰的に考えながらも、一番きちんと見なければならないのは子どもの特性だろうと感じている。中学進学ではまだ親の意向が反映されやすいからこそ、我が子にとってどの選択が最適なのかを見極められるといいなと思う。
「ママ友の間で飛び交う噂や風評に流されるのではなく、授業参観やさまざまな学校行事、担任の先生との面談を通じて、家庭教育で何ができるか考えてみるのもいい」
私も、今後もいろいろな情報を集めつつ、我が子の姿をしっかり観察して、親として寄り添っていきたい。
私も最近読んだばかりですがおもしろかった!ドラマ化もされるそうです。
wmpicaco
最新記事 by wmpicaco (全て見る)
- デジタルフォトフレーム:家族の絆を深める魅力的なインテリアアイテム - 2023-05-25
- 驚きの通話料金!G-Callでスマホからの通話費を半額以下にする方法 - 2023-05-24
- 皮の厚い柑橘類を簡単にむく!夏みかん・いよかん・はっさくに便利な「ムッキーちゃん」 - 2023-05-19