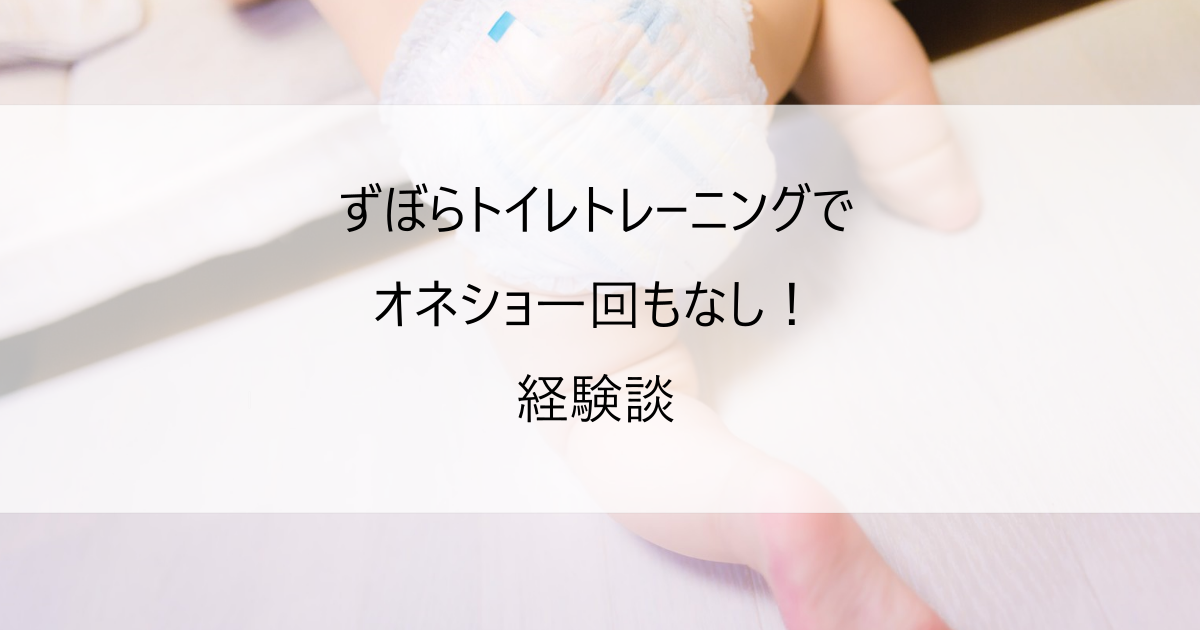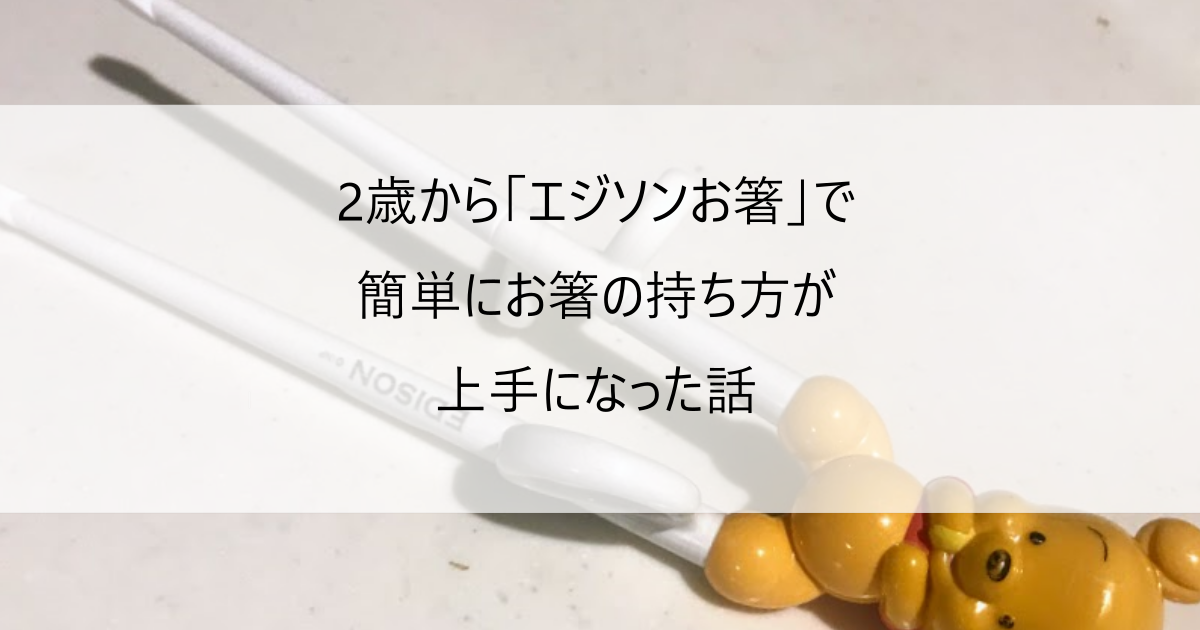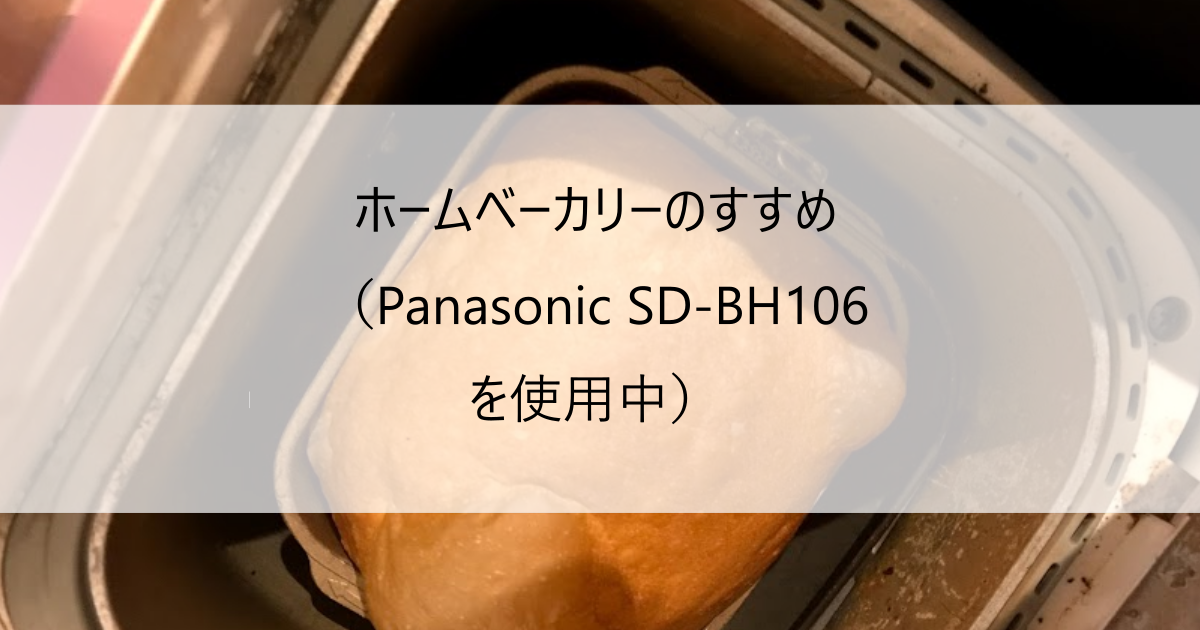こんにちは、ワーママpicaco(@wmpicaco_)です。
我が家は下の子(3歳)のトイレトレーニングがやっと完了しようとしているところ。2歳差の上の子誕生から数えて約6年間に渡るオムツ持ち歩き生活が幕を閉じようとしています。嬉しいようなさみしいような…やっぱり嬉しい。
さてそんな我が子たちのトイレトレーニングは、意外と簡単に済んだな、という感想。トレーニング完了は3歳~3歳半と、比較的遅めだと思います。一言でいうと、トレーニングは適当にしかやってません。ずぼらトレーニング。でも、オムツはちゃんと外れたし、特に恐れていたオネショに関しては、今のところ一回も経験がありません!
(私の中では「オネショ」=夜寝ているときにお布団にしてしまうお漏らし と定義していて、普通の昼間の生活の中でのお漏らしは、何回かあります。)みんなそんなものなのかな?たまたまかもしれない…これからオネショをするのかも?
今のところですが、楽ちん大成功だったと思われる、うちのトイトレのポイントをまとめてみます。(うちの子供たちは保育園児なので、もちろん、楽だったのは保育園の力も借りたおかげ、という部分もあると思います。)
1 周囲のプレッシャーに負けず、ゆっくりめに開始
楽に終わった最大のポイントはこれだったと思う。保育園児なこともあり、「何歳までにオムツを外さなくては!」というプレッシャーはなかった。(幼稚園は入園するときには基本オムツが外れていることが求められると思うが…。)それでも〇〇ちゃんはもうパンツなんだって!という話題を耳にするたび、ちょっとした焦りが… でも、誰だっていつかオムツは外れる。急がなくていいや。と思っていた。
さらにあるのは、おばあちゃんからのプレッシャー。私が子供のころ、30年以上前は、紙おむつは一般的ではなかったらしいですね。そして、1歳台か2歳にはオムツは外れるのが当たり前だったみたい。だから、「まだオムツなの~!」「この夏には外さないと!」と何回か言われたが… ハハハと笑って受け流した。時代は変わったんだし早く外す必要なんてうちにはない。焦ってパンツをはかせてお漏らしをされるほうが面倒だと思っていた。
ちなみにうちの子供たちは2人とも、3歳前後で朝起きてオムツが濡れていないことが多くなってきたので、それをトレーニング開始の目安と考えた。
周囲からのプレッシャーは無視して、子供がその気になったら行かせる。その結果、トレーニングを遅く始めたから楽に短期間で終わった、と私は思っている。どんなに遅くたって発達に問題のない子であれば、小学校に入るまでには外れるでしょーよ。たぶんね。
2 リッチェルの補助便座を使用
子供のお尻は小さいから、2歳ぐらいでそのまま便座に座らせると落っこちてしまう… だから何かしらのトイレトレーニング用グッズを用意するのが一般的。オマルのほうが足が踏ん張れていいとか、自分で座れるように踏み台を用意したほうがいいとか、いろいろ説はあると思うが… うちはこの↓、リッチェルの補助便座だけしか用意しなかった。
3 「できたよシール」は上の子の時だけ
上の子の時はママ友たちからの情報に翻弄されて、「トイレでおしっこやうんちができたら好きなシールを貼れる」手書きのすごろくみたいなものを用意して、トイレの壁に貼っていた。大好きなトーマスやトミカのシールを買って、やってみたものの… できてないのに貼り始めることもあったり、しまいにはマンネリ化したように思う。
その経験を経て、下の子にはそういったものは全く用意せず。トイレトレーニングに限らず、第二子以降って往々にしてそんなものなんじゃないかと思う。
でも、上の子の時のトイトレ手書きスゴロクは、何となく思い出の品と捨てられなくてどこかにしまい込んだ。見つかったら写真撮って参考までにここに載せます。
4 しつこく誘わない
元々、お漏らしを防ぐためには、一定のタイミングでトイレに行かせるのがよいと信じ込んでいた。保育園ではこんな感じでタイミングを決めてトイレに行かせてくれているようである。私も当初は、例えば、
・朝起きた時 ・出かける前 ・お昼寝の前 ・お風呂の前
などでかなりしつこくトイレに誘い、行けば出るから!トイレしないと出かけないよ!と脅したり、抱きかかえて無理やり座らせたり…なんてことをしたこともある。でも、この↓本を読んだのがきっかけで考えが変わった。
関連記事:私の育児バイブル「子どもを信じること」(田中茂樹著)
本の中に、親が先回りして指示をしすぎると尿意すら感じられないようになってしまう、といったようなことが書いてあったのだ。これは極端な言い方だが、この本にはトイレトレーニングに限らず、考え方として、なんでも子供の意思で選択させ、自分で決めさせるのがよい、ということが説かれている。私はそれに共感したのだ。
見ていると、ほっておけばちゃんと、子供は自分で尿意を感じて「トイレ!」と叫び、自ら行くようになるものなのだ。全く誘わないわけではなく、「トイレ行く?」と聞くタイミングもあるが、5歳の上の子も、「行かない!」といったら断固として行かなくて、だいぶため込んだ後に、お漏らしをすることはなくて、ちゃんと自分からトイレに行っている。健康に良いかどうかは置いておいて、朝起きてからトイレに行かずに保育園に着いてからしていることもたまにある。
基本的には、「子どもを信じる」という方針を心掛けている。
5 失敗は責めないで淡々と片付けるのみ
お漏らしは何回かあった。特に上の子が一番多かったのが「パパに怒られショック漏らし」!家ではほとんどこれだったように思う… パパに何かを注意されるとショックの受け方が強いようで…そのタイミングで漏らしてしまうのだ。
6年間も乳幼児育児をしていると、私は感覚もマヒしてきてフローリングに漏らされたぐらいではそんなにショックは受けないようになっていた。トイレの失敗は、責めずに淡々と片付ける、というのは鉄則だと思う。漏らした時点で、子供はやっちゃったな、とちゃんとわかっているし、これを繰り返すうちに、成長していくもので、息子のそんなショック漏らしも次第になくなった。
下の子が漏らしたことはさらに少なくて保育園以外ではまだ1回ぐらいしかない。その時に困ったのが、私は責めたくないのに上の子が責めるのだ!「あ!やっちゃった!漏らした!いーけないんだ~いけないんだ!」などなど…(笑) 正義感なのか自分が褒められたいのかなんなのか… そんな時は、責めないだけなく、「大丈夫だよ、仕方ないよね~。新しいのに着がえよう!」と優しくフォローの言葉をかけることで気持ちを落ち込ませないように対応してみた。
以上、うちの場合のずぼらトイレトレーニングの経験を5つのポイントにまとめてみました。何か少しでも、悩めるママやパパたちの参考になれば、と思います。
wmpicaco
最新記事 by wmpicaco (全て見る)
- 皮の厚い柑橘類を簡単にむく!夏みかん・いよかん・はっさくに便利な「ムッキーちゃん」 - 2023-05-19
- 大豆ミートの魅力とは?ヘルシーで経済的な代替肉の使い方 - 2023-05-18
- 便利で清潔!サラダスピナー代わりに蓋つきボウルとざるを活用 - 2023-05-17