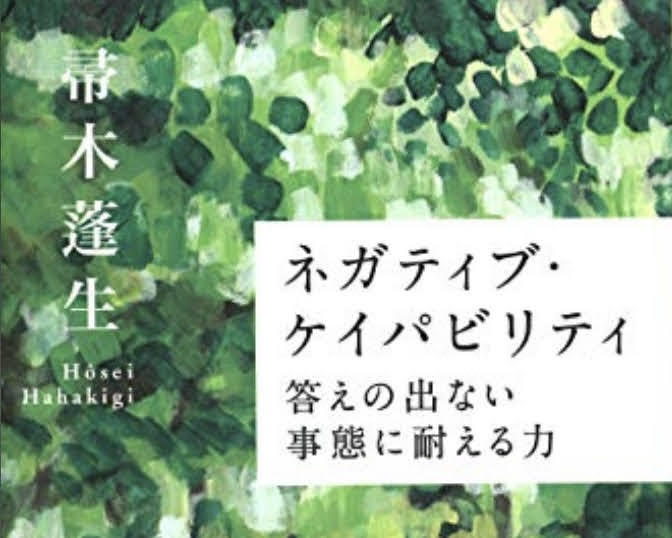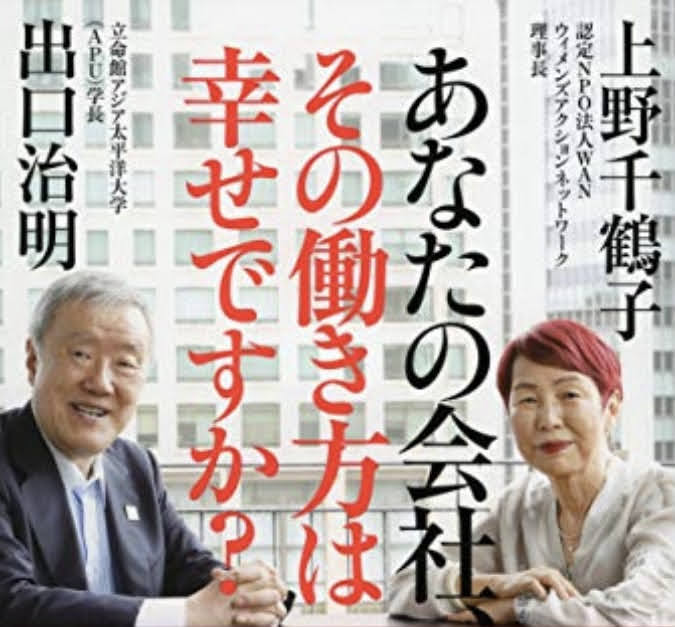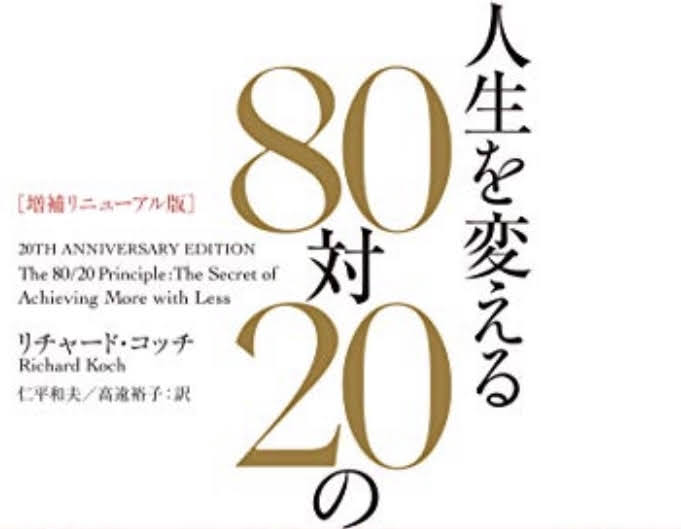こんにちは、ワーママpicaco(@wmpicaco_)です。
「ネガティブ・ケイパビリティ」という言葉を知っていますか?
「ネガティブ・ケイパビリティ」とは、答えの出ない宙ぶらりんの状態に耐える能力、という意味で、私はvoicyの「荒木博行のbook cafe」というボイスメディアの番組でこの言葉を知りました。
そして、これまで自分の中になかったこの概念に結構な感銘を受けて、このことについて詳しく書かれた本「ネガティブ・ケイパビリティ」を読んでみましたのでそのことをまとめます。
created by Rinker
¥1,260 (2024/05/02 10:58:26時点 Amazon調べ-詳細)
スポンサーリンク
1 著者の帚木 蓬生さんについて
著者の帚木 蓬生(ははきぎ ほうせい)さんは、1947年生まれの小説家で、精神科医としても開業されている方です。
数々の小説を執筆されているようですが、私はこの本で初めて帚木さんのことを知りました。東京大学仏文科と九州大学医学部を両方卒業されていて、開業医として活動しながら執筆活動もされている、すごい方なんですね。
2 ネガティブ・ケイパビリティとは?
本での記述によるとネガティブケイパビリティとは「どうにも答えの出ないどうにも対処しようのない事態に耐える能力」を指します。
さらに「あるいは性急に証明や理由を求めずに不確実性や不思議さ懐疑の中にいることができる能力を意味する」とも書かれています。
「ネガティブケイパビリティ」の概念自体は、19世紀に英国の詩人 ジョン・キーツにより発見されたと言われています。しかしその考え方に陽があたったのはキーツが亡くなってから約160年後、第二次世界大戦のころの同じく英国の精神科医ウィルフレッド・R・ビオンによって、だということです。
この辺の「ネガティブケイパビリティ」の成り立ち、歴史といったこともこの本には丁寧に書かれてたのですが、このあたり私は正直そこまで興味を持てなくて眠くなりながらもなんとか読み進めました。
3 ネガティブ・ケイパビリティがなぜ必要か
ネガティブ・ケイパビリティの大切さについては、日本の小説家である黒井千次氏の随筆を引用して次のように語られています。
「謎や問いには、簡単に答えが与えられぬほうが良いのではないか。
不明のまま抱いていた謎は、それを抱く人の体温によって成長、成熟し、更に豊かな謎へと育っていくのではあるまいか。
そして場合によっては、一段と深みを増した謎は、底の浅い答えよりも遥かに貴重なものを内に宿しているような気がしてならない。」
拙速な理解ではなく、謎を謎として興味を抱いたまま、宙ぶらりんの、どうしようもない状態を耐えぬく力。その先には必ず発展的な深い理解が待ち受けていると確信して、耐えていく持続力を生み出すのだ、と。
これを読んで私は、確かにそういう事実はあるだろうな、と腑に落ちた。自分自身、せっかちなところもあって、すぐに答えや結論を出したがる傾向があるなと自覚していた。でもそれは、自分がすっきりしたいだけだった一面もあり、先を急がないほうが良いケースも世の中にはある。むしろそういったことほうが多いのでは?と反省した。
そして、この「ネガティブ・ケイパビリティ」という概念を知り、それが言語化されたことで自分がその状態を耐えられるようになった気がしていて、感謝している。
4 精神科医とネガティブ・ケイパビリティ
「ネガティブ・ケイパビリティ」という言葉、概念を知っているからこそ耐える力が増す、という例として、精神科医としてのエピソードも書かれていた。
——————————
精神科医として受ける身の上相談には、解決法を見つけようにも見つからない、手のつけどころのない悩みが多く含まれている。
主治医はこの宙ぶらりんの状態をそのまま保持し、間に合わせの解決で帳尻を合わせず、じっと耐え続けていくしかない。
耐えるとき、これこそがネガティブケイパビリティだと、自分に言い聞かせる。すると耐える力が増す。
ネガティブケイパビリティを知らなければとっくに逃げ出して、「どうにもならない問題なのでもう来てもらっても無駄です」と言って追っ払っていたかもしれない。
人は誰も見ていないところで苦労するのは辛いもの。誰か自分の苦労を知って見ているところなら、案外苦労に耐えられる。
——————————
このエピソードは「ネガティブ・ケイパビリティ」の効果を理解するのにとてもわかりやすかった。考えてみれば似たような状況は仕事でも家庭生活でも、あらゆるところで存在すると思った。
5 教育とネガティブ・ケイパビリティ
教育におけるネガティブ・ケイパビリティの重要性についても触れられていて、これもすごく勉強になった。子どもの教育を考える親の立場として、このタイミングで理解しておくことができてよかったと思う。
——————————
教育は、問題を早急に解決する能力の開発だと信じられ、実行されてきた。
これは言うなれば、ネガティブケイパビリティとは反対の、ポジティブケイパビリティの育成だった。
学べば学ぶほど、未知の世界が広がっていく。学習すればするほど、その道がどこまでも続いているのがわかる。あれが峠だと思って坂を登りつめても、またその後に、もう一つ高い山が見える。そこで登るのをやめても良いのですが、見たからにはあの峠に辿りついてみたい。それが人の心の常であり、学びの力でしょう。つまり、答えの出ない問題を探し続ける挑戦こそが教育の真髄でしょう。
解決することを答えを出すこと、それだけが能力ではない。解決しなくても、訳が分からなくても、持ちこたえていく。消極的(ネガティブ)に見えても、実際には、この人生態度には大きなパワーが秘められています。どうにもならないように見える問題も、持ちこたえて行く後に、落ち着くところに落ち着き解決していく。人間にはそこ知れぬ「知恵」が備わっていますから、持ちこたえていれば、いつかそんな日が来ます。
「すぐには解決できなくても、何とか持ちこたえていける。それは、実は能力の1つなんだよ」ということを、子供にも教えてやる必要があるのではないかと思います。
——————————
私自身、答えが出ない問題に取り組み続けることに苦手意識があった。勉強の中でも理系の勉強のほうが得意だったのは、「答えがわかりやすく一つに決まっているから」という理由だった。
「ネガティブ・ケイパビリティ」の概念をこれまで知らなかったし、そのことの意味を全く理解できていなかったから、というのもあったと思う。
子どもの教育においてはぜひこの点、意識していきたいと思っています。
「ネガティブ・ケイパビリティ」の考え方をもっと知りたくなった方は、ぜひ読んでみてください。
created by Rinker
¥1,260 (2024/05/02 10:58:26時点 Amazon調べ-詳細)
The following two tabs change content below.

wmpicaco
2人の子どもを育てるアラフォーのワーキングマザー。転職経験なしの会社員。自分が本当にやりたい仕事はなんなのか?を模索しながら暮らしています。
詳しいプロフィールはこちら
最新記事 by wmpicaco (全て見る)
- デジタルフォトフレーム:家族の絆を深める魅力的なインテリアアイテム - 2023-05-25
- 驚きの通話料金!G-Callでスマホからの通話費を半額以下にする方法 - 2023-05-24
- 皮の厚い柑橘類を簡単にむく!夏みかん・いよかん・はっさくに便利な「ムッキーちゃん」 - 2023-05-19