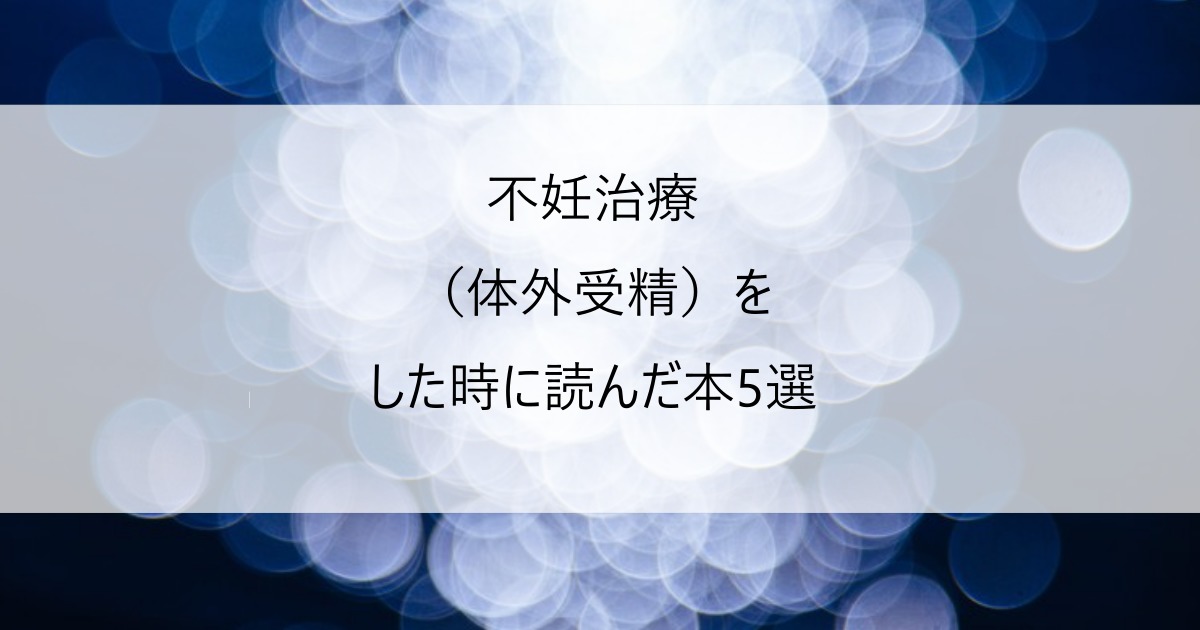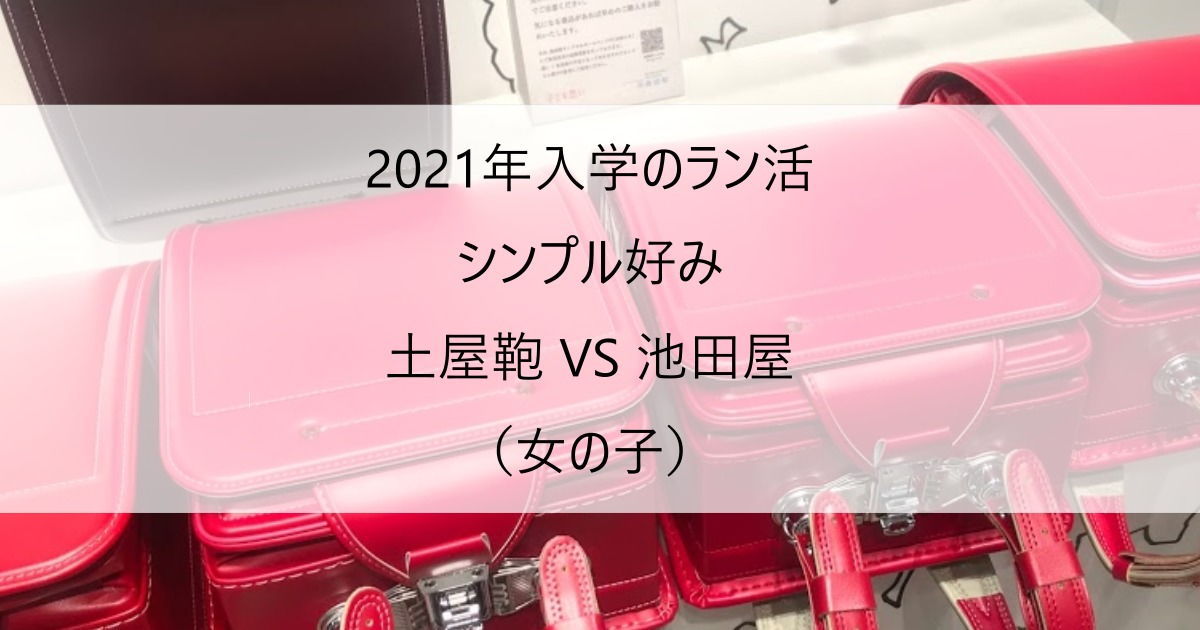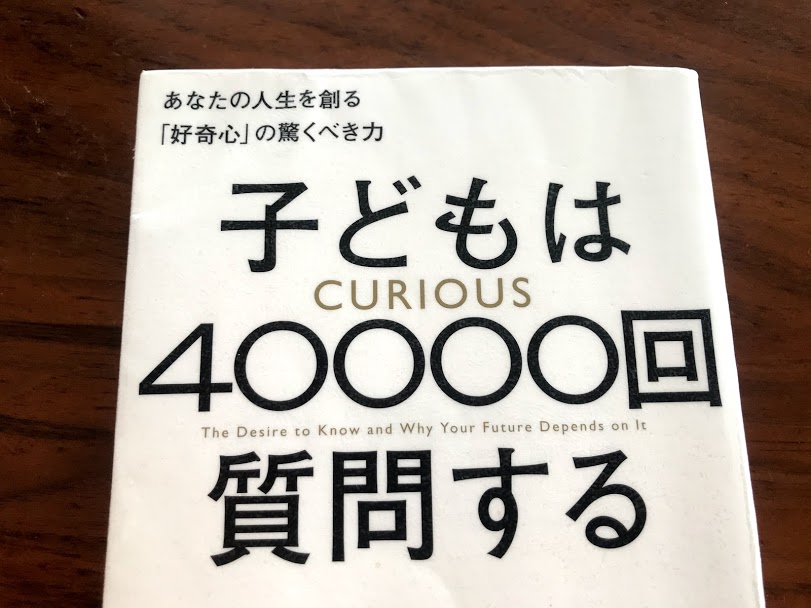こんにちは、ワーママpicaco(@wmpicaco_)です。
私は現在、二児を育てる母親ですが、上の子は不妊治療(体外受精)をして授かりました。今から10年近く前、2011年ごろの話です。
当時「体外受精」をすることへの心理的ハードルもあったし、かなり悩んで色々な本を読みました。技術は日々進歩し、当時の情報が古くなっている部分もあるかもしれませんが、どなたかの参考になればと思い、悩みの中で読んでいた本について当時書いていた別のブログからここに転記することにしました。
私の感想は当時のままにしています。私は「新橋夢クリニック」という不妊治療専門クリニックに通っていたため、その名称を「夢クリ」として記載しているところがあります。そして、治療や病院に関わる記載は通院当時の内容で今とは異なっている可能性があります。
スポンサーリンク
1. エンブリオロジスト-受精卵を育む人たち
「エンブリオロジスト」とは、不妊治療において精子や卵子を取扱う技術者のこと。
私は「培養士さん(=エンブリオロジスト)」という名前を、他の方のブログなどで見かけたことはあったものの実際に会ったことはないし、ほとんど知らない存在だった。
不妊に悩む私でさえこの状況だから、世の中全般にはほとんど知られていない職業であり、
実際、体外受精を行った患者にも、エンブリオロジストから直接受精卵の説明を行う病院もあるが、そうでなく、全くの裏方の役割となる病院もあるという。
生命の誕生にかかわる精神的にも重圧のある仕事でありながらまた、患者の卵の成長によって労働時間が左右されるという、体力的にも過酷な仕事でもある。
本にはその仕事に使命感や志を持って取り組んでいるエンブリオロジスト達が登場する。
彼らもまた、私たちと同じように、妊娠が成立しなかったときにとてもがっかりする、ということに驚いた。
筆者の方も不妊治療の経験者であるとのこと、本の語り口からもそれが伝わってきて、随所に出てくるエピソードには感動した。
日本で初めて体外受精による赤ちゃんが誕生したのが1983年。私が生まれた後のことだ。
エンブリオロジストという仕事には学会での認定資格はあるものの、国家資格はないらしい。
不妊に悩んだ当初は遠い世界に思えた体外受精が、最近ではすぐそこに見えてきて、始めはあった抵抗感もだんだん薄れて、当たり前のことに思えてきていた。
でも、改めて不妊治療の歴史ってまだ浅いんだなってことを感じた。
本の最初には2009年に起きた受精卵取違えのことも出てくる。こういった事件(事故)も、自然妊娠だったら絶対に起こりえないことだが、体外受精をすることで可能性が0ではなくなる。
そんな世界に最前線で取り組んでいる方々には本当に頭が下がる思い。
これからますます自分がお世話になるかもしれないけど、感謝の気持ちを忘れないようにしなくては、と思った。
2. 不器用
野田聖子さんが不妊について告白した「私は、産みたい」は読んだことがあり、今回は、彼女がその後、離婚に至るまでを書いた「不器用
」を読んでみた。
不妊治療や流産の経験談が中心だった「私は、産みたい」と比べて、どちらかといえばそれを包含した、自らの生い立ち、政治家としての活動、結婚、離婚、など彼女の人生全般を振り返って描いたものだった。
政治家という職業は特殊なもので、自分の人生とは全く異なるけど、恋愛や不妊治療中の苦悩など女性としての感情の部分は共感できるところが多かった。
衝撃的だったのは、元夫が家を出て行ってしまった後、野田さんは最後の望みをかけて内緒で元夫の凍結精子を使って治療を行なった、というところ。たぶん道徳的によくないこと…でもその気持ちがわかる気がした。
何をしてでも子供が欲しい、子供さえできれば全てが解決する、などと思ってしまい、冷静に考えられなかったんだと思う。
Amazonのレビューを見ると、野田さんに対して厳しい意見が多い。
そこまでして子供が欲しいなんてエゴとか、その齢で子供を作れるという間違った情報を与えるなとか…
いろいろな意見があることは自然なことだと思うけど、政治家という立場に不妊治療の経験者がいて、こうして情報を発信し、活動してくれるのは貴重なことだと思う。
出生率の低下がニュースになると、晩婚化による出産の先送りとか、不景気でお金がないから産めない、などの理由ばかり出てくるけど、不妊問題にもっと焦点を当ててもいいんじゃなかろうか…。
当事者であるせいもあるとは思うけど、最近、本当に不妊に悩む人の多さを実感する。
一部の、特別な人だけの問題ではなくなっていると思う。
社会問題としてもっと大きくとりあげられて、保険や助成の制度が充実してくれればいいな。
この本の出版から約3年後、彼女はアメリカで卵子提供を受け、2011年1月に男児を出産。
子どもは胎児の段階から重い障害を持つことがわかり、誕生後に何度もの手術を繰り返し現在も入院中。
野田さん自身も出産後に子宮の摘出手術を受けたとのこと。
壮絶・・・。
近いうちに出産後に出版された「生まれた命にありがとう」も読むつもり。
3. 流産の医学
「流産」— 自分が経験するまでは、こんなに世の中でたくさん起こっていることだなんて全然知らなかった。
何度も流産を繰り返してしまう人がいるということも、もちろん知らなかった。
自分はまだ1度しか経験がないけれど、この先妊娠できたとして、再び流産をしてしまう可能性もある。
不妊のことと同時に、流産や死産のこともますます心配になってきた。
そんな中でこの本「流産の医学」を読んだ。
自分の妻が流産を繰り返した経験を持つ、アメリカ人のジャーナリストが、そのことをきっかけに流産の治療法についての研究やその歴史、様々な事例を取材しまとめ上げた本。
かなり詳しく、医学的、科学的に説明されているので、難しくも感じたけど、勉強になった。
流産の90%以上は受精後8週目までに起きる、とのことから、この「命の最初の8週間」についても詳細に説明されていて、命の誕生の神秘、みたいなものを改めて感じた。
自分が不妊に悩むことなく出産できていたら、ここまでの知識を得る機会はなかっただろうな。
夢クリでも処方される排卵誘発剤フェマーラが、新しい薬、として説明されていたり、
PCOSと流産の関係についての研究が紹介されていたり、自分と関係がありそうな部分は特に興味深かった。
また、1940年代から約30年間、「流産予防薬」として使われたDESという薬が、のちに産まれた子供の膣ガンや子宮奇形の原因となることがわかり、使用が禁止されたという話は、とても怖かった。
医者はもちろん、流産から母親と赤ちゃんを救おうとして薬を処方したことだろう。母親は医者を信じて、結果的に出産できた時には感謝をしたに違いない。それなのに、子どもが成長して、その薬に害があったことがわかるなんて・・・ 患者は何を信じればいいのか。どのように医者を選んだらいいのか。答えは見つからないけれど、いろいろ考えさせられた。
著者はあとがきの中で、「私はこの本を、人間くさい要素と科学的な要素がからまりあった本にしたかった」と述べているけど、その通りの内容だったと思う。
4. 生まれた命にありがとう
5. 不妊治療はつらくない
加藤レディースクリニック(KLC)の院長の著書「不妊治療はつらくない」。
夢クリの院長先生は、KLCの元副院長で、考え方の基本は同じだろうから、読んでおこうと思った。
他の不妊治療のやり方をバシバシ斬って終わりかなー、なんて予想していたけど、整然とした医学的な説明に加えて、意外と感情に訴えてくるような文章もあり、通院後の精神的不安定な時に読んだせいで、読みながら号泣してしまった!
もう、この先生も、夢クリの院長先生も、不妊界の救世主にしか見えない…!
でも、Amazonのレビューにも、信者になりすぎるのは危険、みたいな意見もあって、確かにそこのところは気を付けたいと思う。
もっと早くこの本に出会っていれば…という思いも頭をよぎったが、
何年か前に読んでいたらここまで自分の心に響いていたかどうかわからない。
自分にはまだ関係のない話…なんて、希望も含めて思い、読み流してしまったかもしれない。
はじめは自分が不妊であることを認めたくなかったし、そもそも関係する本を手に取ることすらしなかったように思う。そう考えると、自分が今、この本を読んだことに納得できる。
本の中にヒューナーテスト良好で不妊の場合は人工授精は意味がない、というような説明があったけれど、今の自分に当てはまるケース(ヒューナーテスト不良、抗精子抗体陽性or陰性、頸管粘液問題なし)に対する見解がなくてちょっと残念・・・。
まぁ、夢クリに通院しているわけだし、そこで診断してもらえばいいのだけれど、
なんとなく曖昧な判断をされそうな気がして不安だったからそんなことも思ったりした。
当時を思い出しながら感想を読んで行くと、身近な誰かには相談しづらいデリケートな内容なだけに、読書によって知識の面でも精神的な面でもかなり助けられたんだなと思う。
悩みの中にいるどなたかの参考になれば、と思います。
wmpicaco
最新記事 by wmpicaco (全て見る)
- デジタルフォトフレーム:家族の絆を深める魅力的なインテリアアイテム - 2023-05-25
- 驚きの通話料金!G-Callでスマホからの通話費を半額以下にする方法 - 2023-05-24
- 皮の厚い柑橘類を簡単にむく!夏みかん・いよかん・はっさくに便利な「ムッキーちゃん」 - 2023-05-19