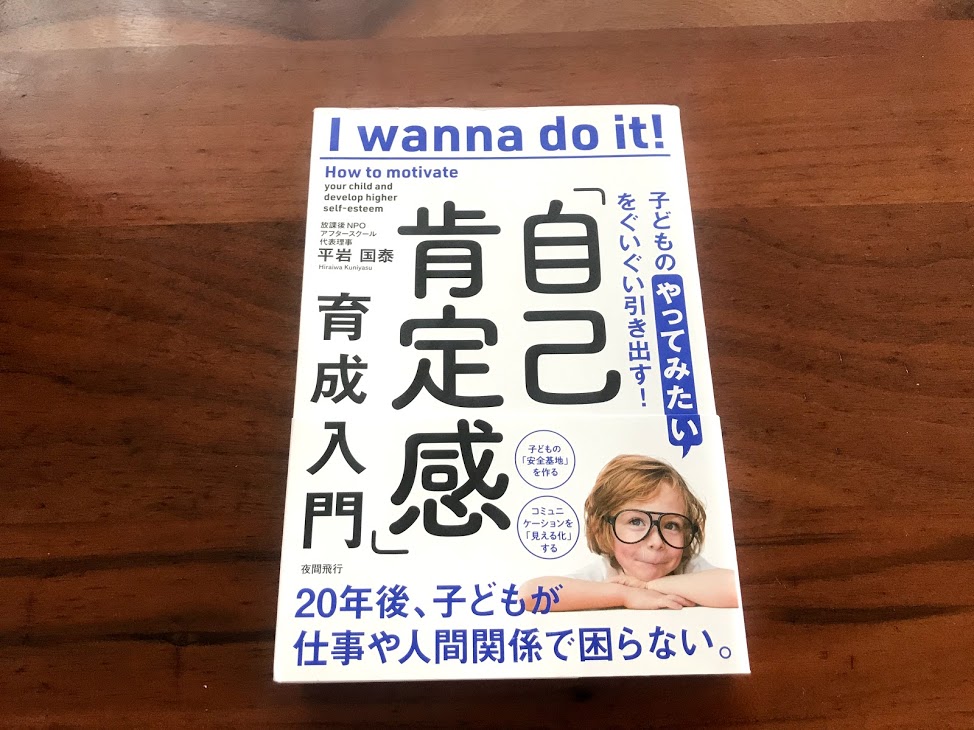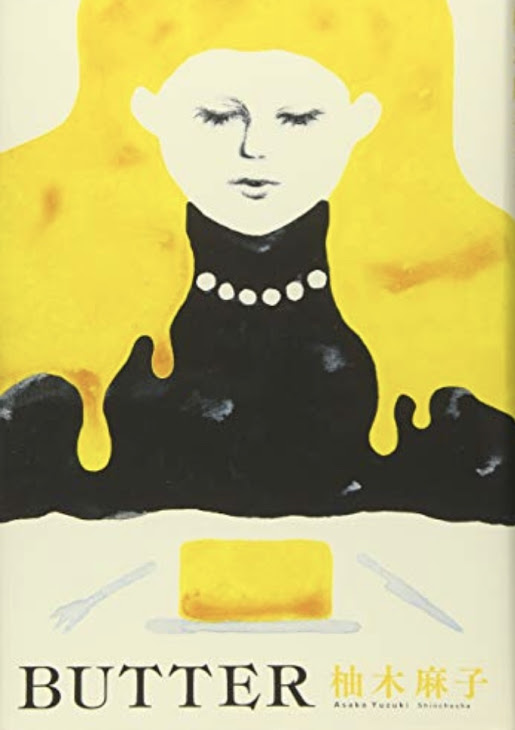こんにちは、ワーママpicaco(@wmpicaco_)です。
育児界隈では最近ではもう使い古されたかと思うほどよく聞く「自己肯定感」という言葉。その自己肯定感を子どもに育む上での基礎とも言える本「自己肯定感育成入門」を読みましたので、自分の子育てに活かしたいと思った内容をまとめます。
自分の行動を振り返りつつ、子どもにとって良くない働きかけをしてしまっていたかも、と気付かされたり、具体的にどのように心がけたら良いかが書かれていて参考になりました。
スポンサーリンク
1 自己肯定感の大切さ
自己肯定感とは、「自分を肯定する力」と本では書かれていた。
私は自己肯定感について、「自分自身が大切な存在だと感じられること」だと理解している。最近は自己肯定感とは別に「自己効力感」という言葉も聞くことが多い。これは「自分にもできると思える力」「失敗しても立ち直っていけると実感できる力」だと認識していて、この本では自己効力感のことも含めて「自己肯定感」と定義して、子どもにそれを育む親としての働きかけ方について解説されていると感じた。
冒頭に、
『親が未来の子供の幸せに対してできることは究極的には一つだけ。自己肯定感を育てること』
だとあった。私もだいたい同意見。親から自立した時に、自己肯定感を持ってモノゴトに対処していくことができれば、それが子ども自身の幸せにつながるのかなと思う。
家庭でしっかりと子どもの自己肯定感の「基礎」となる部分を作ることが親の私の役割だと思っている。これは、勉強や生き方のテクニックを教えることよりもよほど大切なことで、やりがいのあることだ。
2 比べるなら他人でなくその子自身と
他の子や兄妹と比べて評価をするのはよくない、というのはだいたいわかる。
本にも「塾や学校などで、自分より上のレベルの子がいるということは(わざわざ親が言わなくても)身をもって知る」と書かれていたが、子どもの様子を見ているとそのとおりだと実感する。
例えばうちの息子は保育園時代には足が速いと言われていたけれど、小学校に上がるにあたり4月1日に初めて学童に行った瞬間に、自分より足の速い子がいた!と衝撃を受けて自信喪失した?感じで帰ってきた。このように、子どもは周囲の様子を思った以上に観察して、自分との比較をしょっちゅう行い、自分の実力レベルを理解しているものだと思う。
だからこそ、子供のうちは無条件で認められる場所、安全基地を作ることのほうが重要とのこと。そして「比較対象を外ではなく、内側に持つという事が必須条件」つまりやるべきことは「他の子と比べるのではなく、以前の、その子と比べる」ということだと本では書かれていた。
他人と比較するのは良くないということはわかっていても、以前の自分自身と比較して成長を言葉にすることが、自己肯定感育成につながるとはあまり考えたことがなかったので、今後特に意識していきたい。
例えば、誕生日や年末などの節目で、子供は1年前と比べてみるのが良いらしい。さかのぼりりすぎても近すぎても効果が薄くなり、半年から1年前との比較がおすすめだそうで、その頃の写真を見ながら話をするのも良いようだ。
子どもの今より小さい時の写真を見ながら話をする、という意味だとうちではデジタルフォトフレームをリビングに飾っていて、これが結構よい。印刷したアルバムだとなかなか開かないけれどこれだと、家に人がいる時間帯だけタイマーでスライドショーが流れるようになっていて、気がつくと「これはどこ?いつの写真?」と家族の会話につながっている。写真と一緒に子どもが赤ちゃんの頃のことを思い出して、話題にすると嬉しそうにする子どもを見ていると、これも自己肯定感を育む一歩になっているような気がしている。
ポイントは大抵の子供はその成長に自分では気付けないということ。親が「前より成長しているじゃない」と声をかけることで初めて成長しているんだと気づくことができる。「加えて自分の中での成長そのものを大事にし、楽しめるようになる」
という解説で、これまで知らなかった事実に気付かされ、自分の育児にもぜひ取り入れたいと思った。
3 褒め方について
褒めるのが良いとわかっていても、私はあまり人を上手に褒められない気がしている。「すごいね!」「やったね!」とお決まりの言葉を繰り返すのみでなんとかならないものか?と思うほど…
そんな中、「成功しなかった時、失敗した時にこそ、褒める意味が生まれる。」ということには特に注意したいと思った。普段から「失敗は次に繋げるために必要なことで、いいことなんだよ」とは伝えるようにしていて、子どもの失敗を責めたりすることはないように努めているけれど、「失敗したときこそ褒める」というのができていたかというと、怪しい。
「最後まで諦めず頑張ったことは最高に良かった」「今日は誰よりも早く良く走った、すごい」などと力いっぱい褒めるべき。そうした声かけを繰り返すことで、結果ではなくプロセスの重要性が伝わる。
と、どのように褒めるのが良いかも書かれていたので参考にしていきたい。
また褒める態度もそれと同じぐらいあるいはそれ以上に重要だそう。褒める時は、笑顔で、優しく、こっちを向いて、という三つのポイントに気をつけてみると、子どもの心により言葉が届く。そういえば、子どもによく「優しく言って」とか「ニッコリして言わないと嫌だ」とか言われることがある。表情や態度は思った以上に影響があるのだな…
4 気持ちを言葉にする練習
自分の気持ちを言葉にすることも重要だと強調されていた。これは子どもに限らず日本人全般が苦手なことなのかな?と感じる。私自身も到底得意とは言えない。さらに、我が子達も例えば「どうしたいの?」と聞いても、「わからない」とか「・・・。」となることも多くまだまだ気持ちを言葉にする訓練は足りていないように思う。
『自分の気持ちはそもそも言葉にしないと周りに伝わらないということ。その結果、自分の意向が運よく通る時もあるし、残念ながらそうでない時もあるということ、そうした経験を積み重ねることで、子供は自分の気持ちをしっかりと言葉で伝えることの重要性、同時に周りの人の意向も尊重することの重要性も学び、両者の間で上手く折り合いをつけるコツを少しずつ覚えていく。』
という文を読んで、納得した。そして具体的に心がけるとよいこととして、以下のことが挙げられていたので記録しておきたい。
・「言葉にしないと何も伝わらないよ」という態度で、子供が自分の気持ちを言葉にして発するのは根気よく待つこと。
・土日は何をして過ごしたいか、今日の夜は何を食べたいかなと要望をゼロから訪ねてみるのもいい。
・子供に欲しいもの行きたい場所を聞くときに必ずその理由を3つ説明させる。
子供は必死であの手この手で説明する、なになにしたいというシンプルな気持ちを出発点に言葉を組み立てて説明させるというのは、子どもにとって無理のない、なおかつロジカルシンキングの第1歩になる習慣。
「ホワイトボードのコミュニケーションツール(コミュニケーションを見える化し、時間がない中でもコミュニケーションを濃密にしていく工夫)」についても紹介されていて、もう少し子どもたちの年齢が上がり、機会があったらうちでも取り入れてみたいなと思った。
お互いにちょっとした電話やメッセージを書く、今日は何があったか嬉しかったこと悲しかったことなどをお互いにその日の出来事を報告する、メッセージでもらったら、その返事を書いておくと家族間の良いコミュニケーションになる。
例えば、時間的にも直接の会話という意味でもすれ違いが多くなってくる時期には良いのかも知れない。
そういえば、昔私も思春期の反抗期の頃によく母親からの置き手紙をもらったなぁ..となんとなく思い出した。
また、気持ちを言葉にすることとはまた別だが、「子どもの聞く力を鍛えること」も重要だと言う。
このトレーニングとして有効なのが、
「子供にルールや説明をひとしきりした後に質問をする(今した話を一言で言うと?子供に聞いてみると」)」ということ。質問することで、子どもがじっくりと耳を傾け、親が何を伝えようとしてるのかをより真剣に考えるようになるとのことで、これは大人でも同じことなので効果は必ずあると思った。実践するように心がけたい。
5 型にはめる言葉を使わない
「型にはめる言葉はできるだけ使わないこと」というのには少しハッとした。自分は無意識にこういうところはパパにそっくりだね!とか、こういうタイプだよね!とか言いがちだと思った。
本では、「自分はこういう人間だ、こういうタイプだと繰り返し言葉にしたり思い込むことで自分の能力や性質を努力で変えることは難しいという感覚に陥ってしまう」と言う。
特に、子供のうちはそうした方にはめ込まない方が大きな成長に繋がる。既存の型にはめ込むことなく、人は変われる、成長できる可能性があるということを根気よく伝え続けるのが良いとのこと。
無意識に癖のように言ってしまっている言葉を変えるのは難しいかも知れないが、少しずつでも変えていこうと思った。
自己肯定感が大切だってわかっているけど、具体的にどうしたら育つのかわからない。今の子どもへの関わり方で大丈夫かな、と心配な方はぜひ読んでみてください。
wmpicaco
最新記事 by wmpicaco (全て見る)
- デジタルフォトフレーム:家族の絆を深める魅力的なインテリアアイテム - 2023-05-25
- 驚きの通話料金!G-Callでスマホからの通話費を半額以下にする方法 - 2023-05-24
- 皮の厚い柑橘類を簡単にむく!夏みかん・いよかん・はっさくに便利な「ムッキーちゃん」 - 2023-05-19